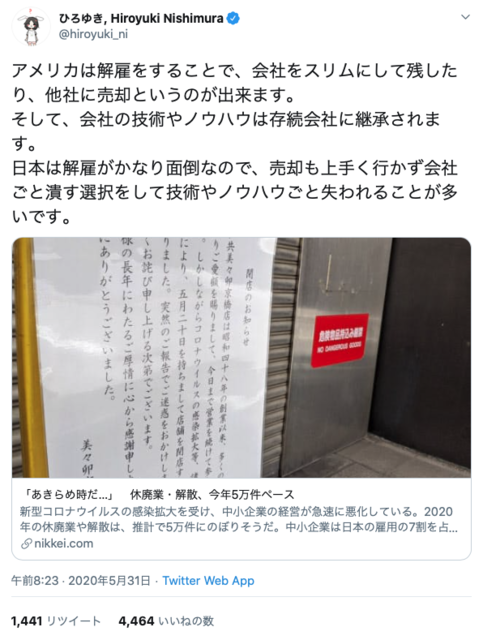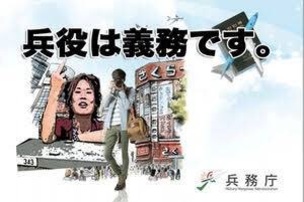新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中小企業の経営が急速に悪化している。2020年の休廃業や解散は、推計で5万件にのぼりそうだ。
中小企業は日本の雇用の7割を占めており、5万社がなくなれば失業への懸念も高まる。雇用や資金面での政府・自治体の支援策を、中小・
零細の企業に早急に行き渡らせることが必要だ。
調査会社の東京商工リサーチによると、新型コロナによる直接的な影響で倒産した企業が29日までに192社となった。20年の倒産合計は、
7年ぶりに1万件を超える見通しだ。
だがこの数には、支払いの遅れなどがないまま事業をたたむ休廃業や解散は入っていない。経営者の高齢化や人手不足で事業承継問題が
深刻化し、16年から休廃業と解散は年4万件以上の高水準で推移している。
そこにコロナによる需要減が追い打ちとなり、20年の休廃業と解散は19年比15%増の5万件に膨らむと推計する。00年の調査開始から
最多だ。景気回復時期も見通しにくく「廃業や解散がさらに増える可能性もある」(同リサーチの原田三寛氏)。
「コロナがなければ、別の展開もあった……」。山形市の漬物店、丸八やたら漬。1885年創業で、市中心部にある国の登録有形文化財の蔵と
一体になった店は街のシンボルだ。だが観光客の急減で4〜5月の売上高は例年の6割減となり、31日に閉店して6月末メドに解散すると決めた。
建物だけは残す計画もあったが、コロナで立ち消えになり、土地を売却して金融負債を返済する。新関芳則社長(66)は「倒産して従業員や
取引先に迷惑をかける前に自主廃業した方がいい」と話す。
中小・零細企業が自主的な休廃業を選ぶ理由について、東京商工リサーチの原田氏は「新型コロナがもたらす変化に対応するには投資が必要。
弱っている中小はそれができない」と指摘する。
「あきらめ時だ」。うどんすきで知られる料亭「東京美々卯(みみう)」。大阪本店から1973年にのれん分けした東京法人は、清算の道を
選んだ。外出自粛などで足元の売り上げは9割減り、20日に首都圏の全6店を閉めた。「コロナは長期化する。このままだと倒産のリスクが
出る」(担当者)と判断した。
高齢化した経営者の廃業への決断をコロナが後押しした面もありそうだ。19年に休廃業や解散した代表者のうち、84%が60歳以上で39%が
70歳代だった。「借り入れや保証融資を受けても返済が心配で、事業を続ける意欲がない。デジタル対応も難しい」(弁護士)
4月に廃業した東京・銀座の老舗弁当店も、後継者がいなかった。70歳に近い店主は「設備投資をしても、回収できる見込みがなかった」と
肩を落とす。
(続く)
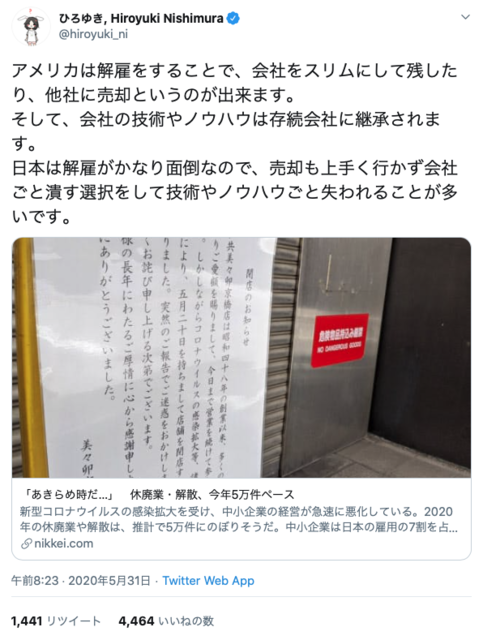
返信する